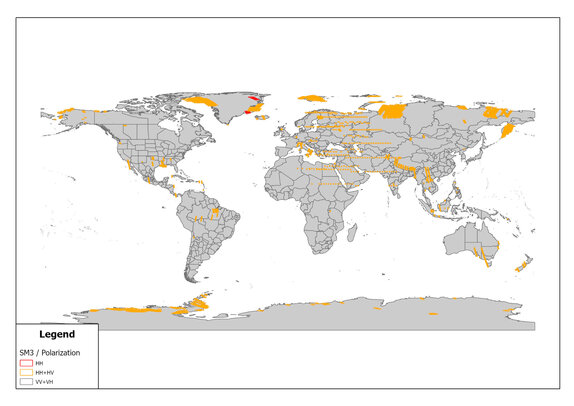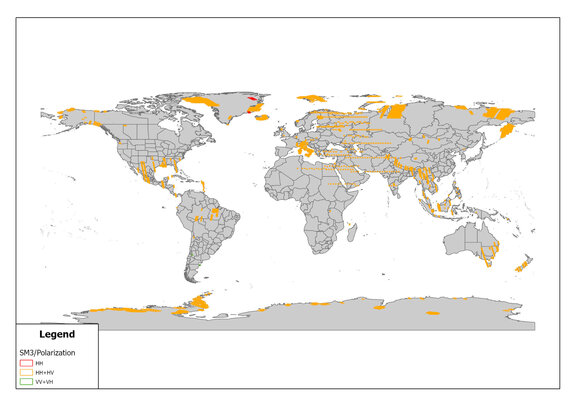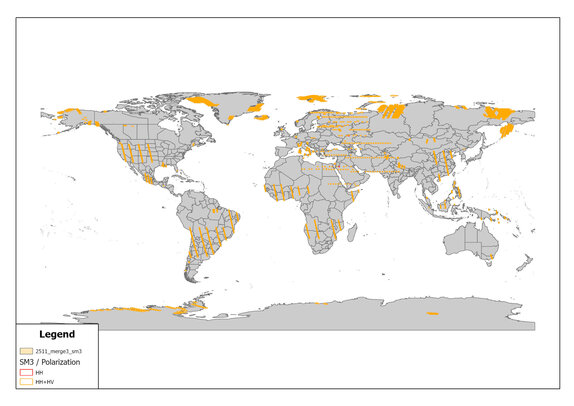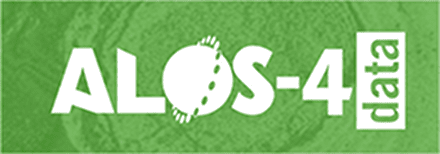ALOS-2「だいち2号」(Advanced Land Observing Satellite 2)はALOS「だいち」の後継機です。ALOSで利用された地図作成・地域観測・災害状況把握・資源探査という幅広い分野において発展的にミッションを引き継ぎます。
ALOS-2主要諸元
| 設計寿命 | 5年(目標7年) |
|---|---|
| 打上日 | 2014年5月24日 |
| 打ち上げ ロケット |
H-ⅡA24号機 |
| 射場 | 種子島宇宙センター |
| 軌道(高度) | 628km(軌道上) |
| 周回時間 | 約100分 |
| 回帰日数 | 14日 |
| 衛星質量 | 2,100kg以下(推薬含む) |
|---|---|
| 衛星サイズ (軌道上) |
約10.0m×16.5m×3.7m |
| ミッション データ 伝送 |
直送伝送及び データ中継衛星経由 ※現在は直送伝送のみ |
| PALSAR-2 (周波数) |
Lバンド(1.2GHz帯) |
技術実証ミッションとして船舶自動識別装置(AIS)信号受信器(SPAISE2)、小型赤外カメラ(CIRC)を搭載しています。
ALOS-2のセンサーについて
ALOS-2は、昼夜や天候によらず陸域観測が可能なフェーズドアレイ方式Lバンド合成開口レーダ(PALSAR2)という地球観測センサを搭載しています。
mission
ALOS-2の主要ミッション
暮らしの安全のため
災害を監視
-
01

地震による
地殻変動を把握 -
02

世界の災害
情報の
提供に
よる国際協力 -
03

豪雨による
水害・
土砂災害
にも迅速に対応 -
04

海・山問わず
災害を監視 -
05

海氷監視
地球規模の
環境問題への対応
-
01

全球森林マップ
による
森林監視 -
02

森林伐採の監視
-
03

極域の氷の
減少監視
経済・社会への貢献
-
01

食糧供給の
円滑化 -
02

地下資源の探査、
地盤沈下の把握
ALOSからALOS-2へ進化
- 01より広く、より詳細に―分解能・観測幅、共に大幅に向上―
-
PALSAR-2はスポットライトモードが追加され、分解能が1~3mまで向上しました。
これは、衛星が進行方向に電波の照射方向を変えることで、対象地域の長時間観測が可能になったためです。(PALSARは最高で10m)。 01 - 観測幅を十分に確保するために、世界最先端の技術である「デュアルビーム方式」を採用しました。これにより高分解能モード(分解能3m)で観測幅50km、スポットライトモード(分解能1~3m)で25kmの観測幅を確保できるようになりました。 02
- 02より迅速に―高い即応性を実現―
-
観測可能範囲が879km→2,320kmに大幅に拡大
ALOSでは、SARアンテナが進行方向右下側に向いており、その方向しか観測できませんでしたが、ALOS-2では、観測可能な範囲をより広くするため、アンテナ面が衛星直下を向くように変更し、観測時に衛星の姿勢を進行方向に対して左右に傾けることで衛星の左右どちらの側も観測できるようにしました。 01 - 回帰日数が46日→14日と大幅に短縮(観測すべき場所にすぐに行ける) 02
- データ伝送能力を強化・高効率化(データ送信の迅速化) 03
以上の改良によって、国内で災害が発生し緊急観測の要求があった場合は、最短2時間程度で被災地の様子を撮影した画像を提供できるようになりました。